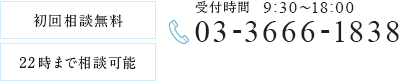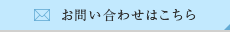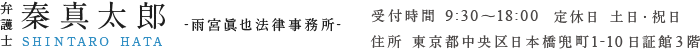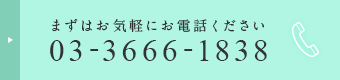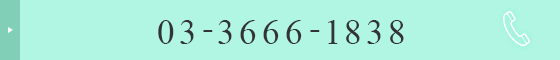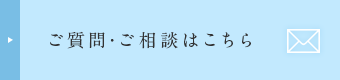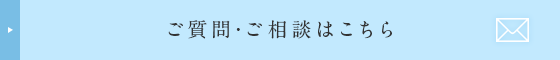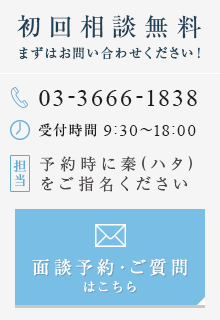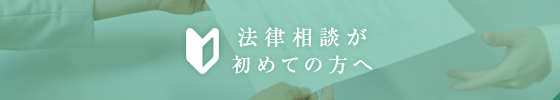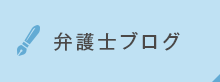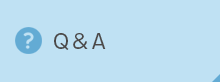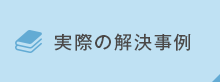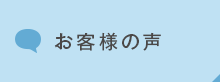【夫から我が子への虐待(4)】子供への「心理的」虐待の証拠決定版はこちら!
2024.02.26更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.児童虐待とは?
どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等
今回は、上記の4つの児童虐待の中でも「心理的虐待」に絞って解説していきます。
2.子供への心理的虐待(モラハラ)って?
モラハラについては 「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと定義されたりしますが、これだけではピンと来ない方が多いと思います。具体的にお子様との関係での夫の発言や行動で「モラハラ」と評価し得るものとしては以下のようなものがあります(これが「モラハラ」の全て、というわけではなく、あくまで代表例とお考え下さい)。
なお、夫がお子様に直接手をあげるケースは、もはやDVに該当しますので、一旦モラハラとは分けて考えます(以下では、このようなDVにまでは達していないケースを想定して解説いたします)
(1)お子様に対して暴言を吐く
お子様へのモラハラの典型例のようなケースですが、より詳しく見ますと以下のようなものがあります。なお、暴言やあなたやお子様ご本人に向けられるケースだけでなく、パパ友やママ友、お子様の友人等が集まる場所等で発言されると、より一層お子様は傷つくことになると思います。
①お子様を侮辱するような発言をする(「バカ」「アホ」だとかの単純なものから、お子様の容姿を侮辱するもの、お子様の学習能力や知識不足等を侮辱するものなどがあります)
②お子様に危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)
③叱責する際などに敢えてお子様が傷つくようなことを言う(例えば「テストの点が悪かったから、おまえのこのゲームは捨てるからな」、「朝の勉強をさぼっていたから、週末はお出かけ禁止な」とか「遊びに行ってる暇があったら、ドリルを1ページでも進めとけよ」等)
(2)執拗な責め立て等
これもお子様へのモラハラとしてはよく見られるケースですが、より詳しく見ますと以下のようなものがあります。
①些細な問題を執拗に責め立てる(「この前のテストで90点だった理由をしっかりと説明しろ」「昨日音楽の笛を学校へ持って行き忘れたことの反省文を書け」「この前の誕生日会で俺に恥をかかせたことについて、参加者に謝ってこい」等々)
②責め立てが何時間も延々と続く
③責め立てが夜中や早朝など時間を問わず長々と続く
④責め立ての際、正座や土下座を強要する
(3)物への八つ当たり等
例えば、機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)といったものです。
特にお子様が大事にしているものとか、お子様のデスクや衣装ケースなどを傷つける行動は、お子様にもショックが大きいと思います。
(4)行動監視や強要
例えば、以下のようなものがあります。
①お子様のスマートフォンにGPSアプリを入れて頻繁に位置情報を確認してくる
②門限その他家庭内のルールを作って、お子様に強要する(勉強の時間は何時からとか、入浴の時間は何時からなどと細かく決めた上で、1分でも過ぎると執拗に責め立ててくるとか)
③お子様が口にするお菓子等について夫の気分次第で種類や値段を制限してくる
このように、一口にお子様へのモラハラと言ってもいくつかの態様があるのですが、いかでは、特に暴言といった形態を中心として、どのようなものが証拠になるのかを解説していきます。
2.やはり確実なのは録音データ
DVのケースですと、怪我を負わされるケースが多いため、診断書や怪我の部位を撮影した写真がもっとも確実な証拠と言えます。これに対して、モラハラの場合には目に見える怪我は残りませんので、診断書や写真を準備することはできません。
そのため、相手がどのような雰囲気でどのような言葉を発したのか、こちらからの発言に対してどのように抵抗してきたのかと言ったところを正確に記録できますので、その意味で録音データは確実な証拠になるといえます。
なお、録音をする場合には以下の様な点にも気を付けながら実施して下さい。
(1)録音は前後の会話も含めて当時の状況が分かる形で録音した方がよい。
たまに相手が暴言を吐いている数秒、数十秒の録音データをお持ちになる方がいますが、これでは、相手が暴言を発する経緯や、あなたやお子様がどのように反応したのかといった点が分かりません。
また、暴言部分のみのデータですと、こちらで編集したデータであると言った形で、相手から争われる危険性もあります。
そのため、相手が暴言を発する際には、その一部始終を録音し、相手がどのように暴言を発し始めたのか、あなたがどのように対応したのか、相手がどのような形で落ち着いていったのかと言った点をすべて録音できるとベストです。
(2)録音データは複数あった方が心強い
モラハラ夫の暴言のフレーズは、「いつも同じような発言が多い」ということもあります。
しかし、同じフレーズばかりだから、「1回だけ録音しておけばよい」とか「この前録音したのと似た様な録音だから削除する」と言うことは絶対にしないで下さい。
まず、複数録音しておくと、相手が頻繁に暴言を吐くと言うことを正確に裁判官に伝えることができますので、その意味で「同じフレーズでもデータの数は多いに越したことはない」ということになります。また、フレーズは似通っていても、そのときの雰囲気や様子はそれぞれ別な場合がありますし、あなたの反応やお子様の反応が異なる場合もあります。このような点は弁護士といった法律の専門家でなければ、違いを判断できないと言うこともありますので、複数録音データがあると、活用方法は拡がる可能性があります。
3.メールやLINE
例えば、夫があなたに対してお子様のことを非難するメールを送ってきたとか、夫がお子様に直接送ったメールでモラハラ発言をしてきたというような場合、有力なモラハラの証拠になります。
ただ、このようなメールやLINEのやり取りですと、旦那の普段の声の大きさ、声のトーンやその場の雰囲気までは伝わらないため、どうしても、録音データよりは証拠としての価値が落ちる面はあります。それでも、メールやLINEの文面から明らかにお子様を誹謗中傷する内容のような場合には、十分モラハラの証拠にはなります。
LINEやメールに関しては、バックアップをきちんと取っておくことに努めて下さい。と言いますのは、メールやLINEをスマートフォンでしか保存していないと、スマートフォンが故障した場合には、記録がなくなってしまいますし、場合によってはモラハラ夫によってスマートフォンを壊されてしまい,そのことで証拠がなくなってしまう危険性があるのです。
バックアップの方法としては、問題となるメールやLINEをスマートフォンで開き、スクリーンショットをパソコンアドレスに送信するといった方法がオーソドックスかと思います。LINEのやりとりをSIMカードにてそのままパソコンに移行しても文字データのみになってしまうことが多いと思います。相手がメールやLINEの内容を否定しなければいいのですが、相手が否定した場合、文字データのみですと、簡単に改変できるデータになりますので、相手から「このデータは偽造されている」とか「一部家内の都合が悪いところが削除されている」といった言いがかりを付けられるリスクがあるので注意が必要です。
また、あなた自身が、お子様のモラハラ被害の内容を親友や親族に対してLINEやメールで相談してきたという場合、内容次第ではモラハラの証拠になり得ます。なお、どの程度モラハラの立証に役立つかは、LINEやメールの文面はもちろん、タイトル名、相談しているモラハラ被害の具体性、文面全体の位置づけ等を考慮する必要があります。
4.物の被害
物に深刻な被害が生じた場合、モラハラと言うよりDVに近くなる様にも思えますが、モラハラの延長で、夫が投げつけてきた場合、破損した物は証拠になり得ます。例えば、旦那が投げつけたために大破したスマートフォン、夫が殴りつけて空いた壁の穴、夫が何度も蹴りつけるためにバラバラになってしまった洗濯籠等、壊れた物の写真も一つの証拠にはなります。
ただ、これらの写真に関しては、例えばスマートフォンの場合、子どもがふざけていて割ってしまった等、相手が言い逃れをしてくる危険性があります。また、あなた自身が直接暴力を受けた証拠にはなりませんので、その意味では証拠の価値は落ちると言わざるを得ません。
5.子ども家庭支援センター等への相談記録
モラハラ夫の暴言に悩まされている場合、その間に子育て支援センターにご相談されている方もいらっしゃいます。そのような場合には、相談した際のやりとりがセンターの方に保管されていますので、その記録の開示を受けると、証拠になり得ます。
なお、モラハラの証拠としてどこまで利用できるのかは、その開示された資料の内容次第と言うことになります。
たまに、私のところに相談に来られる方の中には「大変なことがなければ子ども家庭支援センターに相談するはずないんだから、相談をしているだけで、モラハラの証拠になりますよね?」とおっしゃる方もいますが、必ずしもそうとは言い切れません。
現状の裁判実務を見ますと、「子ども家庭支援センターに相談した」イコール「大変なことが起こった」とまでは評価されないこともありますので、結局は開示証拠に何が書かれているのかをよく検討して判断すると言うことになろうかと思います。
6.証言
証言といった場合、直接の目撃証言なのか、奥様の話を伝え聞いた話なのかによって、その価値に差が生じます。
例えば、お子様が、当時のモラハラの様子を証言してくれるという場合、お子様はモラハラの場面を直接目撃しているので、いわゆる「目撃証言」になります。他方で、モラハラに悩んでいる奥様が友人や両親に相談していたという場合、友人が「当時こんな相談を受けていましたよ」という証言は、直接の目撃証言にはなりません。
一般的には目撃証言の方が証拠の価値は高いのですが、お子様の証言という場合、目撃したときに何歳だったのか、証言時に何歳なのかといった点の考慮が必要になりますし、お子様の立場も考慮する必要があります。例えば、お子様が離婚に大賛成という場合、父親のモラハラを誇張して話していないのかという懸念も生じ得ます。
いずれにしましても、人間の記憶には限度がありますので、証拠の価値としては録音データ等の方が格段に評価が高いのが実情です。
7.モラハラの証拠が少ない、ほとんどないという場合
もちろん、上記の様な録音データがあれば良いのですが、そのような証拠が少ない、または、ほとんどないというケースも多くあります。これまで優しかった夫が豹変して暴言を吐いてきたことに強いショックを受けた方もいるでしょうし、夫の暴言を受け入れられず、また元の優しい夫に戻ってくれると期待して証拠化できなかったという方もいると思います。
その場合、相手から慰謝料を獲得することは難しくなるとしても、「離婚できない」ということにはなりません。
私の経験上、今ある証拠をもとにモラハラ夫を説得して協議離婚が実現したというケースも多数ありますので、決して離婚を諦めないで欲しいと思います。
ただ、そのような場合、どのようにモラハラ夫と交渉を進めていくのか、どのタイミングで調停に切り替えるのかといった点は、経験豊富な弁護士でないと判断が難しいと思いますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
8.まとめ
・一口に心理的虐待(モラハラ)と言っても複数の態様があるので、どのようなものがモラハラなのかを把握しておく必要がある。
・録音データはモラハラの最有力の証拠になるが、その内容については注意点もある。
・ラインやメールは書き込みの内容次第であるが、モラハラ発言などが直接かかれていれば有力な証拠になる。
・子ども家庭支援センター等への相談記録も記載内容に応じて証拠の価値がある。
・物の被害を写した写真は、直接モラハラの証明にすることは難しいケースもある。
・証言は、録音データ等の証拠に比べると、証拠としての価値は見劣りしてしまう。
・モラハラの証拠が少ないケースでも離婚に向けて戦いようはある。
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: