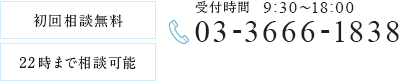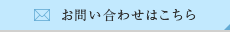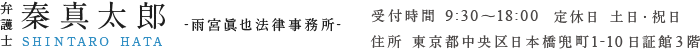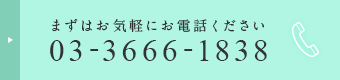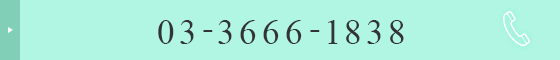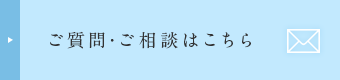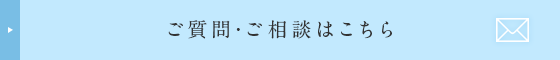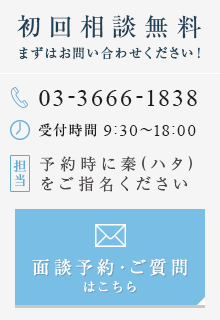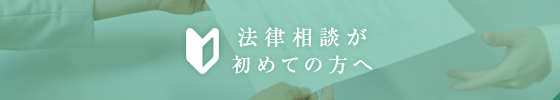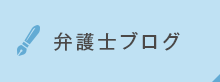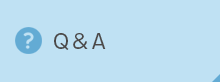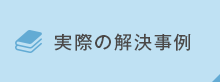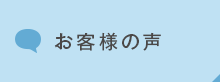こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.弁護士を立てるタイミングは?
すでに調停期日が設定されているときに、弁護士を立てるタイミングとしては、大きく分けて①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておく、②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという2パターンがあると思います。
大きな目安として、私は、奥様が既に弁護士を立てている場合には、あなたも①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておくことをオススメしています。逆に、奥様がまだ弁護士を立てていないという場合には、上記の②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという進め方もあり得ると思います。
奥様が弁護士を立てているかどうかは、裁判所から届いた郵送物に入っている「調停申立書」の氏名欄に弁護士の判子が押されているのか奥様の判子が押されているのかで判断できます。
また、離婚に関連する以下の各条件について意見対立が激しい、または、奥様の要望が強いと感じる場合には、弁護士の必要性は高いかと思います。
①そもそも離婚に応じるかどうか
②子どもの親権をどうするか
③養育費の金額等をどうするか
④面会交流頻度等をどうするか
⑤財産分与をどうするか
⑥慰謝料をどうするか
2.弁護士選びのコツとは?
なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。
そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。
3.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか
一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。
それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。
前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。
ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。
4.旦那側の弁護に精通しているか
私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。
しかし、本当にそうでしょうか。
分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。
そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。
その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。
5.直接会って相性の確認
上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。
直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。
通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。
そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。
6.やっぱり気になる弁護士費用
皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。
ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。
7.弁護士事務所のロケーション
あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。
特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。
8.できれば、弁護士の忙しさの確認も
最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。
オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。
9.まとめ
・弁護士選びのタイミングとしては、おおまかに①第1回期日前から弁護士を立てる、②第1回期日は本人で行ってみるという2つの選択肢がある
・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。
・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。
・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。
・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。
・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる
・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。
関連記事
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック1】調停申立書の読み方
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック2】答弁書の書き方
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック4】簡単に復縁を諦めない
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック5】調停への臨み方
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック9】改善策の組み立て方
>突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック11】面会交流への力の入れ具合
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分