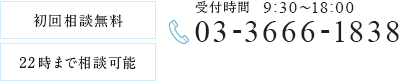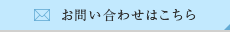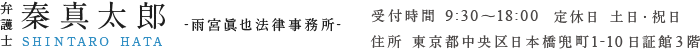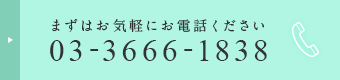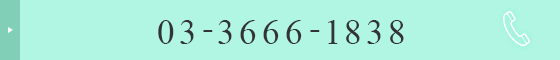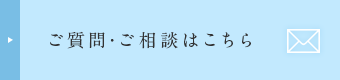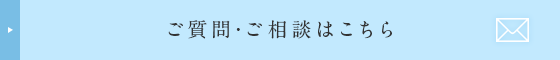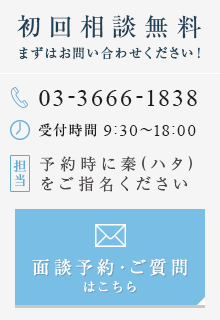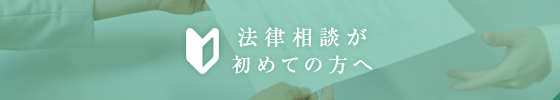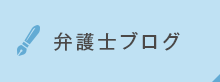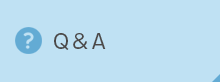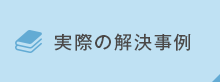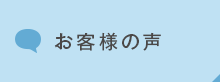【絶対に離婚したくない(19)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?
2023.11.13更新

焦らずに…粘り強く…
食らいつきましょう!
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復のためのまとめサイトはこちら!<<
1.非常に残念ながら夫婦関係修復そのものが難しいケースが多い
あなたとしては、パートナーが突如出て行ってしまい、子供とも離れ離れ、または、子供を置いて行かれ、今後の生活に強い不安を感じるということも多いと思います。
その様な中でこのような話をすることは心苦しいのですが、夫婦関係修復に努めても、残念ながら修復が成功しないケースも多々あります。
もちろん、私が代理人として活動する場合には、修復のためにあらゆる方法を探っていきますが、それでも、最終的には離婚になってしまうことはかなり多いです。
「夫婦関係修復期間」というお話をしますと、「この弁護士にお願いすれば、時間がかかっても夫婦関係を修復してくれるんだ」と誤解してしまう人もいるかもしれませんが、そのように簡単な話ではないということはまず頭に入れておいて頂ければと思います。
2.まず最初にお話するのは「焦らないこと」
前述の通り、あなたとしては将来に対しての不安が強いので、早く夫婦関係を修復したいと考えるかもしれません。
しかし、私の方からは、「焦らないこと」をオススメすることが多いです。
残念ながら、あなたが弁護士に相談しようと考えているということは、「相当深刻な状況」のことが多いです。
そのため、あまり焦ってしまいますと、夫婦関係の修復そのものが上手くいかなくなってしまうことも多いのです。
このように、焦ると夫婦関係修復の可能性がゼロになってしまうこともありますので「焦らないこと」をオススメするのです。
3.修復ありきで強気に出ないこと
私が相談に乗っておりますと、妻が突然出て行ってしまったとか、夫が弁護士を立てて離婚を突き付けてきたという場合でも、何故かご本人が強気で、「相手の離婚要求なんてねじ伏せてしまって下さい」とか「とても本気だとは思えませんので、軽くあしらって下さい」などと言ってくる方もいます。
ただ、相手の「本気度」を見誤ってしまいますと、夫婦の関係は余計にこじれてしまって、夫婦関係修復の道が完全に閉ざされてしまうことも多くあります。
非常に残念ながら、私が実際に担当したケースでも、夫婦関係の修復に導くことができたのは、「ほんの一握り」というのが実態です。
そのため、夫婦関係修復そのものがそれなりに難易度が高いものだということはしっかりと自覚した上で対応していく必要があります。
4.修復までに要する期間はケースによってかなり差が大きい
私が直接担当したケースや、私が相談を受け、ご本人が対応することで修復に結び付いたケースなどを見ておりますと、修復までに要する期間は、「かなりばらつきが大きい」というのが率直な感想です。
ただ、手続きがどの程度進んでしまったのかに応じて、一定の傾向などをお示しすることはできますので、以下解説していきます。
5.【ケース1】相手が弁護士を立てずに対応したケース
相手が突如別居を開始してしまったり、調停を起こしたりなどしたが、結局弁護士を立てなかったケースです。
このケースですと、夫婦関係修復までにあまり期間を要しないケースも多い印象です。
本当に短期間のケースですと、①妻の短期間の家出ということで1か月くらいで解決しました、とか、②夫の海外出張に同行するという大きな決断をすることになりましたが、同行して生活していくと円満な家庭を築けていますといったお話を伺うことも多いです。
他方で、夫婦関係の軋轢が深く、①一旦はこのまま別居させて欲しいと言われてしまい半年は別居期間が続きました、とか、②調停委員からもあまり焦らない方が良いと言われてしまい、1年別居を経ての同居再開という条件になってしまいました、といったお話を聞くこともあります。
6.【ケース2】相手が弁護士を立ててきたケース
相手が弁護士を立ててきたケースですと、残念ながら、夫婦関係修復の可能性が下がる傾向が強いです。
相手も弁護士を立てているくらいですから、離婚の意思が強いことが多く、どうしても夫婦関係修復に向けての話し合いに進まないことが多いのです。
私が実際に担当したケースでも、夫婦関係修復までの期間は様々という印象でして、①半年ほどの調停期間を経て無事に同居にまで結びつけられたというケースもあれば、②調停自体は4か月ほどで終了したのだけれども、そのあと2年ほどが経ってようやく家族同居にこぎ着けたというケースもあります。
7.【ケース3】相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきたケース
はじめにお話しておきますが、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすということはできません。特別な事情がない限り、まずは、離婚調停という手続きを踏んだ後でないと、離婚裁判を起こすことはできないのです。
このようにして、相手が離婚調停を起こし、その後、離婚裁判まで起こしてきたという場合でも、相手の離婚請求棄却、要するに、裁判所から「現時点では離婚不相当」という結論を得たことはあります。
ただ、その場合でも、夫婦関係の修復に結び付いたのかと言いますと、残念ながら、冷却期間が長引いているだけとなってしまうことが多いかと思います。
離婚裁判はそれ自体がお互いにとって負担が大きく、結論として「現時点では離婚不相当」という結論を得ても、なかなか夫婦関係修復の道筋を描くことが難しいのです。
8.まとめ
・私の方からは、まず「焦らないこと」をお伝えすることが多い。
・修復ありきで強気に出ると、夫婦関係修復そのものの可能性がゼロになってしまうことが多いので、注意が必要である。
・修復期間はケースによって様々なので一概に期間を申し上げることは難しい。
・相手が弁護士を立てずに対応した場合、比較的、修復期間は短期間のケースが多い印象である。
・逆に、相手が弁護士を立ててきた場合には、修復そのものが難しいケースも多く、また、修復の期間はさまざまである。
・相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきた場合、仮に結論としてこちらが勝訴しても、修復の道筋は描きにくいことが多い。
関連記事
>【絶対に離婚したくない(18)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?
>
>【絶対に離婚したくない(20)】相手が浮気している可能性が高いが、どうすれば良いか?
>
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: