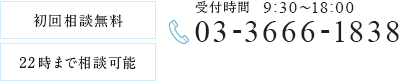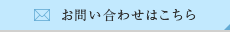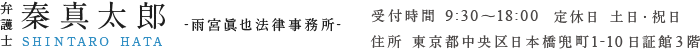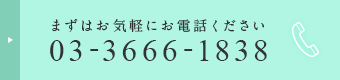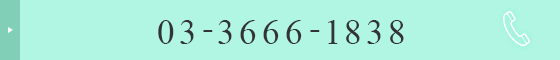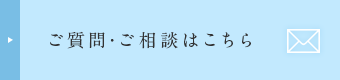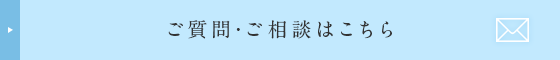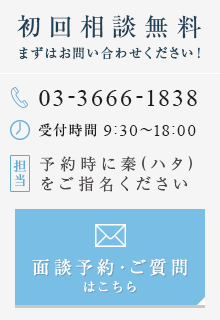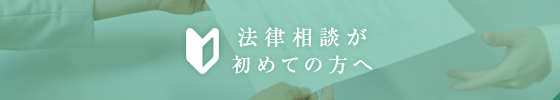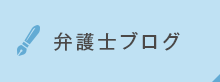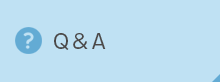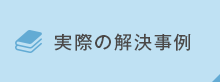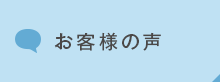損をしない財産分与の心構え
2016.03.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.財産分与って何? .
財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。
ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。
例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。
ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。
このような不公平を解消するものが財産分与になります。
2.損をしない財産分与の心構え
損をしない財産分与の心構えとして一番大事なのは、「いざ離婚の場面になった場合、相手が財産を隠す危険性がある」という認識を持つことです。
離婚の場面になりますと、ご夫婦お互いに夫婦生活での不満を相手にぶつけることになりますので、お互いに良い感情を持っていません。そうしますと、なるべく相手に渡すお金を少なくするべく、財産をできる限り見付からないようにするということが起こりうるのです。
つまり、いざ離婚の話し合いになった際、「うちの旦那は株をやっているから株式をもっているはずだ」とか「預金通帳にそれなりの蓄えをしているはずだ」と言いましても、相手から、「株は別居の1年前からやっていない」だとか「預金は会社の接待で使ってしまって残っていない」と言われてしまう危険性があると言うことです。
このように相手が言い逃れしてきた場合に、こちらが何も具体的な話をできませんと、交渉はストップしてしまいます。
3.どのような点に注意をしていればよいのか。
普段の生活で心がけて欲しいのは、相手に宛てて届く郵便物の把握になります。
なお、郵便物は相手宛の郵便になりますので、決して勝手に開封しないようにご注意下さい。封筒の外観だけでも銀行名・支店名等は把握できます。
具体的にお話ししますと、それなりの金額の預金を持っている場合には、その銀行から「定期預金に切り替えてはどうか」だとか「投資運用の相談に乗ります」といった形の勧誘の封書が届くことが多いです。そのため、その様な封書が届いていれば、その銀行のその支店に預金通帳をもっていると言うことになります(なお、預金については「○○銀行」という情報だけではなく「○○銀行○○支店」という情報まで把握しておく必要があります)。
また、株式投資などを行っている場合には、定期的に株取引の取引報告書が証券会社から届きますので、どこの証券会社で株式取引を行っているかを把握することができます。
4.相手からの「私は蓄えなんかない」という言葉を鵜呑みにしないこと
特に離婚の本格的な紛争に発展している場合、離婚の際の金銭負担を軽くするためか「私にはほとんど蓄えはありません」と言ってくる場合があります。
ただ、普段の生活の中で少ないかもしれませんが蓄えがゼロと言うことはほとんどないと思います。
そのため、仮に相手が普段から「私にはほとんど蓄えはない」と話していたとしても、キチンと預金通帳を確認するなどして、どの程度の残高があるのか把握しておく必要があります。
>>離婚問題を多数手がける弁護士秦真太郎への無料相談はこちら
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: