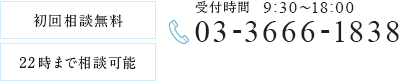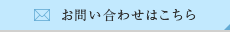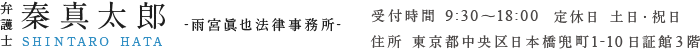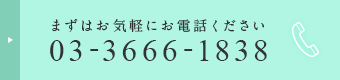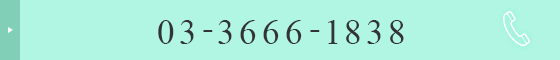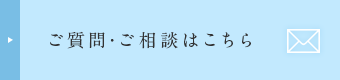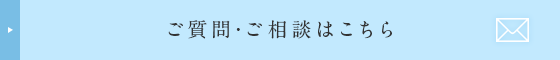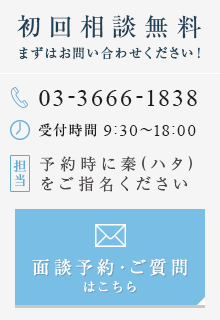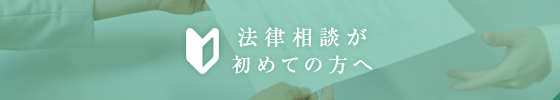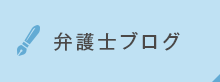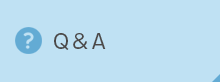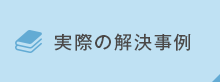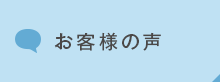【コロナ離婚特集7】離婚までに決めなければならない全事項
2020.04.15更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して、解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.離婚することと親権者が決まれば、離婚届そのものは簡単
夫婦の話し合いで離婚すること及び親権者をどちらにするかを決定することができれば、離婚届自体は完成させられます。
しかし、離婚届にお子様の面会交流や養育費に関わる注意事項(具体的には離婚届の右側中央よりやや下の囲みにあるチェック欄がこれに該当します)が記載されているように、お金の問題などを何も決めずに離婚してしまいますと、後から後悔するというケースも多々あります。
そこで、今回は、本人同士で離婚の話し合いをする場合、どのようなことを話し合わなければならないのかについて解説いたします。
2.離婚の際に話し合う必要がある事項とは?
まず、全体像を把握するためにも、離婚の際に話し合う必要がある事項としては、どのような項目があるのかについて解説いたします。通常は以下の7項目について話し合う必要があります(お子様がいらっしゃらない場合には、(1)、(5)、(6)、(7)の4項目になります)。
(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか
(2)親権者を誰にするか
(3)養育費をどのようにするか。
(4)面会交流をどうするか。
(5)財産分与をどのようにするか
(6)慰謝料をどのようにするか
(7)年金分割をどのようにするか
3.離婚すべきか離婚すべきではないか
離婚することが決まりませんと、離婚の条件の話に進みませんので、一番初めに決めなければならないのが、離婚すべきかどうかという点になります。
コロナウイルスの問題で夫婦関係が不和になったとしましても、そのことを前面に出して離婚を要求しても、旦那様側からは「一過性の問題に過ぎない」という反論を受ける可能性が高いので、コロナの問題が起きる前の状況等を理由に離婚を切り出した方が良いと思います。
4.親権者を誰にするか。
より分かりやすく言いますと、ご夫婦のどちらがお子様を育てていくか、という問題です。諸外国では親権と監護権を分ける例などもありますが、日本では一般的ではありませんので、「実際に今後お子様を育てていくべき人」が親権者になる、というイメージで考えると分かりやすいと思います。
ご夫婦で、今後旦那様と奥様どちらがお子様を育てていくべきか話し合うことになります。
コロナ不和のケースですと、夫側の感染リスクへの意識の低さ等も親権判断の一つの要素として主張していくことになろうかと思います。
5.養育費をどのようにするか。
(1)まずは、養育費をいくらにするかを話し合う。
親権者をご夫婦のどちらにするか決まった場合、離婚後のお子様の生活費等として養育費をいくら支払うかを決める必要があります。
養育費を月々いくらにするのかについては、実務上「算定表」というものが活用されており、具体的な内容は、最高裁判所のホームページなどをご覧いただければ、詳しい内容は分かると思います。
なお、「養育費」というと「毎月いくら支払わせるか」という点に目が行き、他にも決めるべき点について疎かになると言うこともありますので、以下の点にも十分注意して話し合って下さい。
(2)支払い終了時期を何時にするか。
最もオーソドックスな内容としては、「お子様が満20歳に達するまで」となります。
しかし、お子様が大学に進学することを予定している場合、大学卒業までは養育費を払ってもらいたいと考えるのが通常でしょう。特にお子様がまだ幼児であったり小学生の場合には、「大学入学はまだまだ先のこと」というイメージをお持ちかもしれませんが、今決めておかなければ、将来相手が養育費を出し渋る可能性もありますので、「いつまで養育費を払ってもらうのか」について、きちんと取り決めておく必要があります。
(3)入学費用や進学費用等の取り決め
今後のお子様に関する教育費として、私立高校への入学費用や進級時の学費、大学の入学費用や進級時の学費等は重要な問題になります。前述のようにお子様が小さい場合、まだイメージを持ちづらいかもしれませんが、入学費用等は高額なことが多く、月々の養育費では支払いきれないことが多いため、離婚時にきちんと話し合っておくべき項目になります。
ただ、お子様がまだ小さい場合には、「入学や進学の費用の負担について今後きちんと話し合いの席を持つ」といった取り決め方もあり得るかと思います。
他方、既にお子様が私立高校や大学に在学中という場合には、必要な学費の金額等も明らかになっているでしょうから、学費の半分を相手の負担とするといった具体的な数字を取り決めるべきことになります。
6.面会交流をどのようにするか
(1)まずは、面会交流の頻度を取り決める。
あなたがお子様を育てていくと決めた場合、旦那様とお子様とは別々に生活していくと言うことになります。そうすると、旦那様としては、今後どのくらいの頻度でお子様に会うことができるのかについては重要なトピックになります。これが面会交流の問題です。
まずは、面会交流の頻度について話し合う必要がありますが、一般的には1か月に1回か、2か月に1回程度とすることが多いように思われます。
なお、安易に頻繁な面会交流を約束してしまいますと、生活環境の変化(例えば、あなたが遠方に引っ越すことになり、旦那さんの自宅との距離がかなり遠くなってしまった場合とか)等で頻繁な面会交流の実現が難しくなったときにトラブルのもとになりますので、どんなに多くとも、1か月に1回程度で十分だと思います。
なお、令和2年4月現在の状況は、コロナウイルスの関係で緊急事態宣言が出ておりますので、少なくとも緊急事態宣言解除までは、面会交流は控えてもらうという形が一般的かと思います。
(2)それ以上に細かな内容を取り決めるべきかはケースバイケース
面会交流については、相手がどこまでの要望を申し立ててくるかにもよりますが、あまり細々とした内容にしない方が良いケースが多いです。お子様の成長や環境に応じて離婚時とは状況が変化していく可能性も高く、そうすると、あまり画一的に取り決めておかない方が柔軟に対応できるからです。
相手から要望が出されることが多い項目としては、①宿泊を伴う面会交流の要求、②旅行を伴う面会交流の要求、③学校行事や習い事の発表への参加の要求等があり得ます。
7.財産分与をどのようにするか。
(1)財産分与というのはそもそもどんな話なのか
財産分与というのは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産をどのように分けるのかを取り決めると言うことです。
婚姻生活中は、離婚することを見越して準備しているという夫婦はいないと思いますので、通常夫婦の財産は均等ではないことが多いと思います。例えば、奥様が専業主婦で、旦那様が仕事をしているという場合、旦那様名義の預金はそれなりの額貯まっているとしても、奥様の預金はそれほど貯まっていないというケースもあると思います。
そんなときに、旦那様が「これは俺の名義の預金だから離婚の時には、びた一文お前には渡さない」としてしまいますと、内助の功があった奥様にとって酷な話になってしまいます。
そこで、離婚の時には、夫婦どちらの名義になっているかを問わず、婚姻中に築いた財産は半分ずつに清算すべきだというのが財産分与の基本的な考え方になります。
(2)慰謝料とは別問題なのでご注意
離婚に伴うまとまったお金の問題と言うことで、慰謝料の問題と混同している方が多いのですが、財産分与と慰謝料は別の問題とお考え下さい。
即ち、慰謝料というのは、相手に浮気や暴力といった一方的有責性がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝させるものになるのに対して、財産分与は、このような有責性の問題を抜きにして、夫婦の財産を清算しようという話になりますので、別次元の話と言うことになるのです。
(一昔前には、「財産分与の慰謝料的要素として、慰謝料分も考慮する」といった議論をすることもありましたが、最近は、財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料として話し合うのがオーソドックスです)。
(3)実際問題どのような手順で話をすべきか
厳密に財産分与の計算をする場合には、①対象財産の特定→②財産の評価→③総合計額の算出→④分与方法の検討という手順を踏むことになります。
以下具体的に解説いたします。
①対象財産の特定
財産分与は夫婦で築いた財産を分ける仕組みですので、夫婦で築いた財産以外の財産は対象外になります。
例えば、独身時代に貯めていた預金や相続で取得した財産は対象外になります。
対象財産として代表的なものは、婚姻中に購入したご自宅、自動車、預貯金、生命保険や学資保険、株式等になります。
まずは、夫婦で築いた財産としてどのようなものがあるかを割り出して行く作業をすることになります。
②財産の評価
預貯金などは金額が明らかなので問題は少ないのですが、例えば自宅などはいくらになるのかおおよその評価額を調べる必要があります(住宅ローンが残っている場合、通常はローン残高は差し引いて評価することが多いです)。
他にも、生命保険等については今解約したらいくらになるのかを保険会社に問い合わせる必要があります(実際には解約しませんが、いくらの価値があるかを確認するために、保険会社に「今解約した場合いくらになるか教えて下さい」と電話するのです。
③総合計額の算出
上記のように各財産の価値を算出することができた場合、それらの数字を全て足し算して総合計額を算出していくことになります。
例えば、旦那さん名義の資産がご自宅(評価額3000万円、ローン残高2400万円)、学資保険(解約返戻金額200万円)、預金(3つの通帳の残高合計が300万円)で、奥さん名義の資産が預金のみ(2つの通帳の残高合計が100万円)というケースですと、総合計額は(3000万円-2400万円)+200万円+300万円+100万円で、総合計は1200万円になります。
この総合計額を算出する際には、旦那さんの資産だけではなく、あなたの資産分も加算する必要がありますので、ご注意下さい。
④分与方法の検討
前述の例ですと、総合計額が1200万円になりますので、あなたの取り分は半額の600万円になります。
このような600万円の取り分で何を取得するか、あなたの希望を検討することになります。
即ち、自宅の価値が600万円なので、自宅を取得し、同時に住宅ローンの名義もあなたに変更するという方法もあり得ますし、逆に、自宅は旦那さんに渡して、旦那さん名義の学資保険をこちらに名義変更し、旦那さんの預金額全額を取得するという方法もあります。
要するに、取り分の範囲で何を要求していくのかという問題です。
8.慰謝料をどのようにするか
前述しましたとおり、旦那さん側に離婚の大きな原因がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝するためいくらを要求するかの問題です。通常は旦那が暴力をふるってきたとか、浮気をしていたといったケースで問題になります。
この問題は、相手が暴力や浮気を明確に否定する場合もありますので、早期離婚の観点から慰謝料を強く要求しないというケースもありますし、納得いかないので徹底的に慰謝料を強く要求していくというケースもあると思います。
あなた自身のお気持ちに応じて、どこまで要求し、どの程度の金額を要求するか検討してみて下さい。
なお、コロナ不和自体を理由にして慰謝料を請求していくことは一般的に難しいかと思います。
9.年金分割について
旦那様が会社勤めをしており、奥様が専業主婦の場合、当然ご夫婦の年金積立額は大きく異なってきます(旦那様は給料天引きで相当額の厚生年金を支払っていることと思います)。年金分割とは、婚姻中の旦那様の厚生年金支払履歴の半分を奥様に移す制度になります(つまり、年金分割をしておくと、将来年金の支給を受ける年齢になったときに、もらえる年金が増えると言うことになります(旦那様側は逆に減ることになります))。
年金分割の手続のためには、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所にて入手する必要がありますので、事前に準備しておいて下さい。
この年金分割については、夫婦で半分に分けるというのが一般的で、年金分割の合意ができあがったときには、年金事務所に書類を提出しなければいけません。
10.話し合いがまとまったときには必ず離婚協議書を作成する。
前述のように、養育費など離婚後長期間にわたって約束された項目などもありますので、話し合いの内容は必ず離婚協議書という形で書面化して下さい。
この離婚協議書では「当事者間では本離婚協議書に定める他何ら債権債務がないことを確認する。」という一文を入れておけば、後から話が蒸し返される危険性はほとんどなくなります。
11.まとめ
・離婚の際には、以下の事項を取り決める必要がある。
(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか
(2)親権者を誰にするか
(3)養育費をどのようにするか。
(4)面会交流をどうするか。
(5)財産分与をどのようにするか
(6)慰謝料をどのようにするか
(7)年金分割をどのようにするか
・項目ごとに注意事項があるので、注意事項に留意しながら取り決める必要がある。
・話し合いがまとまった段階で、離婚協議書を作成した方が良い。
関連記事
>【コロナ離婚特集1】コロナ離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選
>【コロナ離婚特集2】本人から離婚を切り出す3つのポイント
>【コロナ離婚特集3】コロナ問題での不和は離婚理由になるか?
>【コロナ離婚特集6】夫との別居を決意!別居に当たっての11個の手順
>【コロナ離婚特集8】コロナ不和に内在するモラハラ問題
>「離婚協議書を作ろう」と言ったら「信用してないのか?」と言われた…どう対処すべきか
>別居中の生活費を勝ち取る全手順
>>このブログを書いた弁護士秦に直接問い合わせたい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: