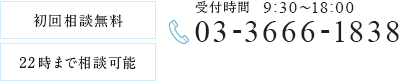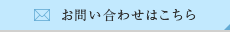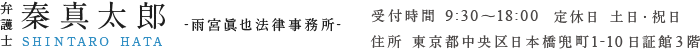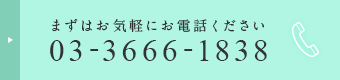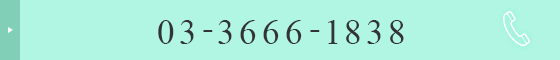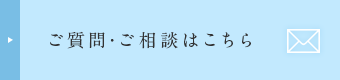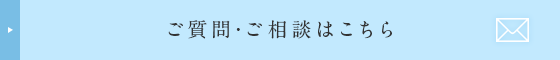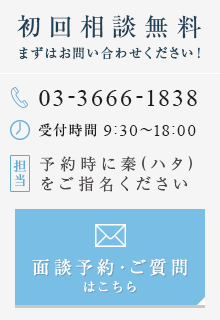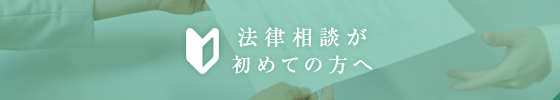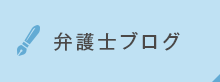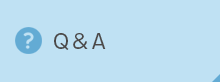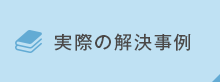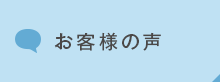モラハラ夫との別居準備(4)―別れ話をした時のモラハラ夫の反応は?
2022.05.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。なお、>>「モラハラの連鎖を断ち切る!!」モラハラ被害女性のための総合サイトはこちら<<になります。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.別れ話をした時のモラハラ夫の反応は?
あなたの方からモラハラ夫に別れ話をした時、どのような反応をするのか、ある程度想定して準備しておけると、あなた自身混乱することも少なくなるでしょうし、今後の離婚に向けての対策につながるケースもあります。
そのため、以下では、私が直接担当した事件で、モラハラ夫がどのような反応を示すのか、夫の反応を踏まえて、どのような伝え方が良いのかといったことを詳しく解説していきたいと思います。
2.【ケース1】モラハラ夫が全く真剣に受け取ってくれない
私が事件を担当していて、モラハラ夫の反応として一番多いと思われるのが、真剣に受け取らないという反応です。
特に、あなたが専業主婦であったり、パート勤務で収入が少ないような場合には、「離婚しても自分の収入だけで生活できるはずがない」などと考えるモラハラ夫が多いようです。
また、これは別れ話のタイミングにもよるのですが、夫婦喧嘩の際などに、別れる旨を話した場合には、モラハラ夫は、こちらが一時的な感情で離婚や別居を口にしたと誤解しているケースも多いです。
このようにモラハラ夫が真剣に受け取らないという場合には、真剣に受け取るような伝え方をしていくのが良いと思います。例えば、お互いの両親を交えた大家族会議のような形式をとるとか、具体的な別居開始日を決定してしまって話をするとか、もしくは、別居開始後に改めて話をするといった方法が考えられます。
3.【ケース2】モラハラ夫が急に神妙になる・謝ってくる
モラハラ夫は、家庭内ではモラハラ発言等ばっかりであっても、家庭の外では、まるで別人のように社交的にふるまうというような人物も多いです。そのようなモラハラ夫の共通点としては、「自分がどのように行動すると自分に有利になるのか」と言ったことを計算できるということです。
そのため、あなたが真剣に別居や離婚のことを伝えると、一旦はあなたを落ち着かせたほうが良いと考え、モラハラ夫は神妙になったり、急に謝ってくるのです。
このような場合によく質問を受けるのが「今は神妙にしているけれども、演技なので長続きしませんよね?」といったご質問です。
私は実際にあなたの夫に直接会ったことも直接話したこともないため確証をもってお話しできないのですが、「これまでのモラハラ行為の重症度に応じて推測するしかありません」とお答えすることが多いです。これまでのモラハラの重症度が重い場合には、残念ながら、今は神妙にしていても長続きしなかったり、モラハラ行為が再燃する確率が高いと言えますし、逆に、これまでのモラハラの重症度がそこまで重くない場合には、モラハラ行為が再燃する確率は高くはないかもしれません。
なお、モラハラ夫がこれまで一度も謝ったことがなかったような場合には、今回初めてモラハラ夫が謝ってきたことであなたも嬉しくなってしまい、安心してしまうということもありますが、残念ながらそれが演技の可能性もありますので、今後も多少なりとも用心しながら生活したほうが良いと思います。
4.【ケース3】モラハラ夫が猛反発してくる
重症のモラハラ夫でよくあるケースですが、あなたが真剣に別れ話をしたことで、猛反発してくるケースです。
そもそも、モラハラ行為をする人間は、自分が悪いことをしていないと考えている人が多いです。「あなたが俺を怒らせるのが悪い」「怒らせる原因を作ったのはあなただ」「あなたの家事があまりに不十分なので注意しただけで、感謝されても責められる謂れがない」といった発想です。
このようにモラハラ夫としては何も悪いことをしていないと考えていますので、突如あなたから離婚や別居を突き付けられて、信じられない思いや、もっと家族円満にできるようあなたの方が努力すべきだなどと強く反発してくるのです。
このような場合、あなた一人でこれ以上別れ話を進展させていくことは難しいですし、あなたのモラハラ被害が拡大していくだけなので、他の親族の協力を得るなど話の持って行き方や、離婚に向けての手順等をしっかりと検討していったほうが良いと思います。
5.【ケース4】表面的に波風を立てないようにしつつ離婚準備を始める
表面的にモラハラ夫側の動きが見えにくくなるので、一番油断がならないケースです(ただ、私が実際に担当した事件でも、このように対応するモラハラ夫はごく少数です)。
例えば、①表面的にはこちらへの圧が大きく軽減されたが、子供への関わりが非常に積極的になったケース(最悪離婚になっても、新件を獲得すべく準備しているケース)、②表面的にはモラハラ発言等が大きく減ったが、預金をインターネットバンキングに変更したり、これまで置いてあった共用スペースから勝手に移動し始めた(最悪離婚になっても、財産分与でなるべくお金を渡したくないので、財産隠ぺいを目論んでいるケース)といったものが考えられます。
モラハラ夫はこちらの予想以上に計画的に準備を開始している可能性もありますので、十分用心する必要があります。
6.上記のケースはあくまで代表例であること
上記で詳しく解説したケースはこれまで私が直接担当した事件での実際の事例なのですが、あくまで代表的なものに過ぎません。
そのため、前述のケースの枠に入らない反応を示すケースもあると思います。
また、前述のケースは、必ずしも、どれか一つのみが当てはまるということではありません。複数が当てはまるというケースも往々にしてありますので、この点も留意が必要です。
7.まとめ
・私が担当した実際のケースにてモラハラ夫の反応としては以下のようなものがある。
①全く真剣に受け止めない
②急に神妙になる・謝罪してくる
③猛反発してくる
④表面的には波風を立てないようにしつつ離婚準備を進める
・これらはあくまで代表例なので、違うケースもあり得るし、複合的なケースもあり得る。
関連記事
>モラハラ夫との別居準備(2)―そもそも、「別居」という選択をすべきか
>モラハラ夫との別居準備(3)―別居前にモラハラ夫にどこまで話をしておいた方がよいか
>モラハラ夫との別居準備(5)―【持ち物リスト】別居の時に何を持って出れば良いか
>モラハラ夫との別居準備(6)―夫から「子どもの連れ去り」と言われないためにはどうすればよいか
>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるのか)
>【弁護士が解説】別居から離婚の話し合いで決めなければならない全事項
>【弁護士が解説】別居後、離婚の話し合いがまとまらない場合に踏むべき全手順
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: