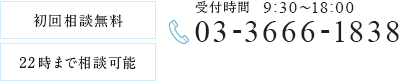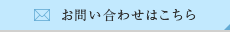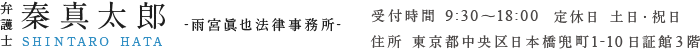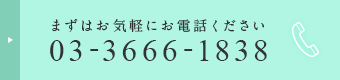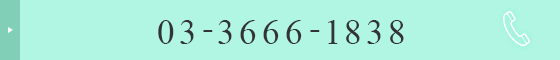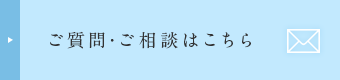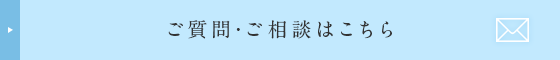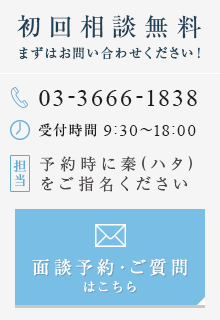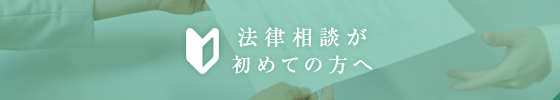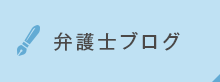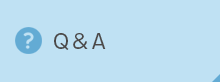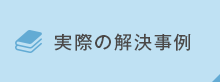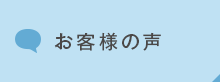【こんな小さい子がいるから絶対に離婚できない(40)】夫婦同居調停って何だ?
2025.12.22更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】
私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。
それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。
①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている
②親の事情で片親というのは子供が不憫
③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう
④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変
⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)
⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい
⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任
⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず
⑨世間体、周囲の目が気になる
このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。
以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。
1.夫婦同居調停って何だ?
インターネットで色々と調べていると「夫婦同居調停」という制度があることについて辿り着くことがあります。ただ、この調停制度について、正確かつ詳細に説明しているサイトは意外と少ないので、夫婦同居調停というのがどのような手続きなのかについて解説していきます。
夫婦同居調停とは、一般的には、夫婦が当人同士で話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦の同居に導くための話し合いの手続などと言われたりします。
しかし、この説明だけでは漠然としていて夫婦同居調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に夫婦同居調停というものがどのようなものなのかをご説明します。
2.そもそもこの調停は何を目指す調停なのか?
通常この調停を起こす場合、ご夫婦の一方が急に別居を開始してしまったという場合に、夫婦の同居義務(民法752条)の遵守を求めていくという手続になります。
調停の席での話し合いが順調に進めば、夫婦の行き違いを調整し、夫婦・家族同居に戻すことを目標にした手続にはなります。
ただ、こちらとしては夫婦同居を求めて調停を起こしても、相手が頑なに夫婦関係の継続を拒否する姿勢の場合、話し合いが決裂してしまうリスクはあります。
3.夫婦円満調停との違いは?
私は、夫婦同居調停のことを聞かれた場合には、夫婦円満調停を、より強力にした調停ですよ、と説明することが多いのですが、大きな違いは以下の3点になります。
①夫婦円満調停だと、ひとまず当面は別居(すぐに同居までは求めない)という選択肢もあるが、夫婦同居調停はあくまで同居を求める手続きである
②相手の「同居義務違反」をより際立たせた手続である
③調停が不成立になった場合には、審判という手続きに移行する
以下詳しく解説していきます。
(1)あくまで同居を求める手続きである
夫婦関係円満調停ですと、相手の意向を考慮して、一旦暫くは別居状態を続けるという形の解決も選択肢の一つではあります。
しかし、夫婦同居調停は、あくまで同居を求めていく調停なので、暫く別居ということは基本的に視野に入れていません。
(2)同居義務違反を際立たせている
同居調停は、夫婦の間に同居義務があることを前提として、その同居義務を守らせようとするものですから、夫婦円満調停以上に「同居義務違反」を際立たせた手続と言えます。
(3)調停不成立になると審判手続きに移行する
夫婦円満調停は話し合いが決裂すると、調停手続きは終了してしまい、「調停がなかった時の状態」に戻ります。
これに対して、夫婦同居調停は、話し合いが決裂すると、調停手続きは審判手続きに移行し、裁判官が結論を出してくれます。
(4)弁護士としては、同居調停はあまりオススメしない
前述の通り、同居調停は、結論を「同居一本」に絞っているため、あなたとしても強く同居を求める姿勢だという決意を示すことはできます。
ただ、同居調停は、元々、相手の同居義務違反を「責める」ことを前提にしていますので、そのことで相手の心情を害するリスクがあります。
また、相手が悪質な背信行為に及んでいるような場合は別ですが、そうでない場合、同居調停が審判移行しても、裁判官が「同居せよ」という結論を出すことは基本的にありません(そのため、審判移行前に裁判官の方から「調停を取り下げて欲しい」と打診されるのが一般的です)。
4.調停を申し立てる前にすべきこと
(1)相手に事前に連絡を取る
いきなり調停を起こしますと、裁判所からの封書が来て相手は驚いてしまうと思います。そのため、相手には最低1回は事前に夫婦同居調停を起こす旨の連絡をしておいた方が良いと思います。
このような事前連絡を行うことによって、相手が話し合いに応じてくる可能性もありますので、極力事前に連絡をしておいて下さい。
(2)調停申し立てのタイミングを探る
前述のような事前連絡をしたところ、相手が交渉の席についてくれるようであれば、一定期間交渉での解決をトライしてみたほうが良いと思います。「もうすでに調停を申し立てる準備をしてしまったので申し立ててしまう」といった心構えではなく、話し合いの余地があるなら、極力話し合いで解決できるよう努めたほうが良いと思います。
夫婦同居を目指すのであれば、今後もご夫婦間の直接のコミュニケーションは非常に重要になりますので、そのための準備という視点からも、直接の話し合いに重点を置いた方が良いでしょう。
5.調停委員ってどんな人?
夫婦同居調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は、同じ時間帯に複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。
では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、司法書士、鑑定士、大学教授、裁判所書記官OBや上場会社の重役OBなどが調停委員になるなどしています。
6.夫婦同居調停ってどこで行うの?
夫婦同居調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、こちらの自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。
裁判所と聞くと、テレビのドラマなどで映し出される裁判所の法廷をイメージする人も多いのですが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。
7.夫婦同居調停って何時行うの?
調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。
この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご本人の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。
ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。
8.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?
1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。
9.当日の調停の流れは?
調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。
①ご夫婦はそれぞれ別々の待合室で待機
↓
②調停委員に事件番号(またはお名前)を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
↓
③夫婦双方が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
※但し、こちらから夫婦で顔を合わせると冷静な話し合いが難しいと事前に伝えておきますと、夫婦同席での手続き説明ではなく、手続き説明は夫婦別々に行われます。(特に東京家庭裁判所では、ご夫婦別々とする形の方が一般的です)
↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
↓
⑧最後に次回期日までの宿題の確認及び次回期日の日程調整をしたうえで、その日の調停は終了。
10.調停室内に入れるのは誰?
よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。
11.調停が開催される頻度は?
調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。
12.そもそも相手は調停に来るか?
調停はあくまで裁判所を利用した話し合いの場になりますので、相手が法律的な出席義務を課されることはありません。
そうすると、相手が欠席するのではないかと不安に思われる方もいますが、家庭裁判所から封書が届きますので、相手も出席してくることの方が多いと思います。そのため、最初から「相手が出てこないかもしれない」と考えて調停を起こさないのではなく、相手も来る可能性が高いものとして調停は活用して行ければと思います。
13.調停が成立した場合の拘束力は?
よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
ただ、これは調停の内容次第です。
例えば、相手に金銭を支払わせるという内容の調停調書には、強制力がありますが、「今後互いを尊重し、コミュニケーションを絶やさず円満な夫婦関係を築くことができるように努力する」と言った条項は、ある意味精神論を謳った条項に過ぎず、この内容に強制力を認めることはできません。 そのため、夫婦同居調停のゴールそのものに強制力はないことになってしまいます。
強制力とは「相手が反対しても無理矢理実行させる」という効力になりますが、国家権力が相手を無理矢理自宅に連れ戻したり、夫として理想的な行動や言動を強要することは人権上問題になりますので、認められないのです。
14.まとめ
・夫婦同居調停は、夫婦同居を目指す手続である。
・夫婦同居調停は、夫婦円満調停を強力にした手続と捉えると理解しやすい
・弁護士としては、夫婦同居調停はあまりオススメしない
・調停委員は40歳以上70歳以下の学識経験者等が就任する。
・夫婦同居調停は、裁判所建物の中の会議室のような場所で行われる。
・調停は平日の午前または日中に行われる。
・1回の調停は合計2時間程度で終わる。
・2時間の調停では最初に手続の説明、その後交互に調停委員が本人から話を聞くなどし、最後に次回までの宿題等の確認・次回期日の設定を行うという手順で進むことが多い。
・調停室には本人しか入れない(弁護士が就いている場合は弁護士も入れる)
・調停は1か月に1回程度の頻度で開催される。
・相手は調停の席に出席する義務はないが、大体の人は出席してくることが多い。
・調停が成立した場合には判決と同じ効力が認められることもあるが、内容次第だし、夫婦同居調停の内容については強制力が認められない条項の方が多い。
関連記事
>【初めてでも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば、平日夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: