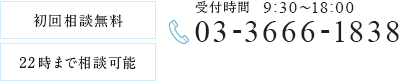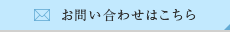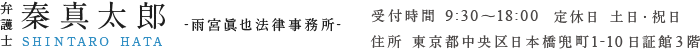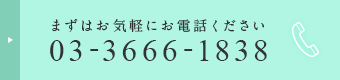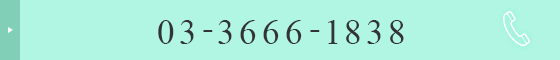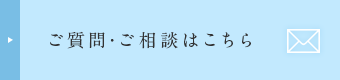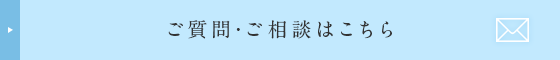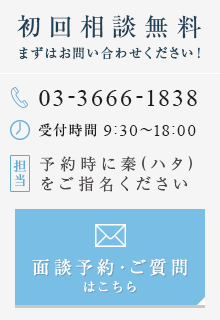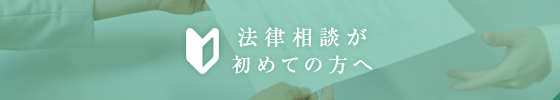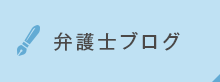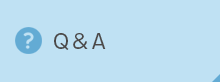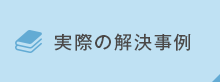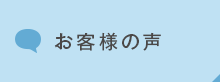【絶対に離婚したくない(32)】相手からの離婚調停(7)―調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか?
2024.08.19更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復のためのまとめサイトはこちら<<
1.そもそも、調停委員ってどんな人がなるの?
調停が始まると、調停室には男性1名、女性1名の調停委員が座っていて、色々と話を聞いてくれたり、相手の話を伝言してくれるのですが、その調停委員はどんな人なのかは気になるところです。
調停委員のなり手としては、弁護士や司法書士、鑑定士、大学教授、元書記官、上場企業の元役員や元部長等々様々です。このように必ずしも家事事件の専門知識を有していない方が調停委員になることもありますので、細かな法律問題についてまではよく分からないという方もいらっしゃるのが現実です。ただ、基本的な調停の進め方や基本的な法律問題の知識は皆様お持ちですし、詳しい法律問題については裁判官の意見を聴くことが多いため、このような形でフォローされることが多いです。
2.調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか
これは調停委員の方の個性が出る部分でもありますので、一概には申し上げられないのですが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員がいるのも事実です。調停委員によっては、こちらのことを「女の敵」と言わんばかりに責め立ててくる調停委員もおりまして、対応に難儀することもあります(ただ、ここまで極端な対応をしてくる調停委員はごく少数ですが)。
ここまで極端に離婚を勧めてこないまでも、大半の調停委員は離婚方向で話を進めたがる傾向が強いです。そもそも、離婚調停では、(夫婦円満ではなく)離婚で調停がまとまるケースが多いため、このような傾向が強まることはある程度致し方ない面があります。
ただ、繰り返しになりますが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員は全体から見るとかなり少数派です。
たまに私が相談に乗っていますと「インターネットで見たんですが、調停委員がこちらの話を全然聞いてくれなくて、離婚条件の話ばかりされた、と書いてあったんですが、本当ですか?」とか「わざわざ妻(夫)は調停までやっているんだから、普通の調停委員は『諦めた方がいいんじゃない?』って言ってくるんですよね?」などと質問を受けることもあります。
このような質問に対しては、「実態として、そこまで極端な進行をされることはごく稀ですので、ご安心ください」とお答えすることが多いです。
3.このような調停委員への対応方法は?
一番の効果的な対処方法は、「離婚には応じられない」というしっかりとした意思と言葉を持って返答し続けることです。こちらが離婚すべきか悩んでいる姿勢を見せてしまいますと、調停委員の議論に巻き込まれてしまいますので、悩んでいる姿勢を一切見せないと言うことが一番大切になります。
このようにこちらの一貫した姿勢を見せていると、調停委員も第2回調停期日以降は大きくトーンダウンするというケースも多いです。
また、こちらが離婚したくないという話をすると大抵の場合、①その理由と②何か改善策として考えていることはあるか?と再質問されることが多いです。
そのため、このような質問が出されることを見据えた上で、予め回答準備をしておく必要があります。
なお、あまりに調停委員の圧が強いような場合には、私の方から「調停委員さん、今のお話は強制とかではありませんよね?念のための確認ですが」などと口を挟むこともあります。調停という手続きの性質上、調停委員は、こちらに何かを強制することはできませんから、調停委員も「別に強制ではありませんけど」と返答してきます。
4.離婚拒否はあなたの「わがまま」ではない
調停委員からあまり強く言われてしまいますと、あなたの方としても、「自分がヨリを戻したいと考えていることは、「わがまま」なのかな?」とか「ひとりよがりなのかも」と感じてしまうことも多くあります。
ただ、離婚してしまいますと配偶者は、法律上「他人」になってしまいます。
これだけ離婚するかどうかはとても大切な話なのです。
あなた自身の人生やお子様の人生にも関わる非常に大切な話なのですから、ヨリを戻したいと考えることは決してあなたの「わがまま」ではありません。
5.調停委員はどこまで離婚理由を話してくれるか?
先ほど解説したような調停委員とは全く正反対で、調整型に徹する調停委員もいます。要するに、相手の方からはかなり詳しい離婚理由等を聞いているのに、その詳しい内容をこちらにあまり教えてくれない調停委員と言うことです。
調停委員があまり詳しいことを語ろうとしない理由としては、①あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらが感情的になってしまうと危惧している、②あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらの言い分を全く信用していないといった不信感を招くおそれがあるといったことが考えられます。
いずれにしましても、このような調整型の調停委員の場合には、大抵、こちらの言い分は親身に聞いてくれるのですが、こちらの言葉が調停委員の心に響いていないことも多いため、注意が必要です。
このような調整型の調停委員を相手にする場合、親身に話を聞いてくれるため、こちらの感情を話しがちなのですが、そうではなく、過去にあった具体的事実について話をした方が効果的なことが多いです。
6.調停委員が注目しているかどうかはメモを取るかどうかで判断できる
調停委員によってはほとんどメモを取らない調停委員もいるのですが、大体の調停委員は、こちらの言い分を詳しくメモすることが多いです。
ただ、調停を重ねていくと、これまでと重複した話やこちらの感情に関わる話は段々と調停委員もメモを取らなくなっていきます。
こちらの話を親身に聞いてくれるからと思って色々と話をしても、調停委員がほとんどメモしていないという場合には、調停委員は「あまり新しい話は出ていない」とか「今回の問題を解決するに当たって参考にならない」と考えている可能性がありますので、注意が必要です。
7.まとめ
・調停委員は色々な有識者がなる。
・ごく少数ではあるが、調停委員によっては強烈に離婚を勧めてくる調停委員もいる。
・いずれにせよ、離婚に応じたくないのであれば、離婚に応じないとはっきりと発言することが最重要である。
・ヨリを戻したい理由や改善策を質問されることもあるので、事前に準備しておくと安心である。
・ヨリを戻したいとの意見を述べることは決してあなたの「わがまま」ではない。
・調整型の調停委員だと奥様の離婚理由等の詳細を語ってくれないことも多いので注意が必要である。
・調停委員の関心の高さは、メモの量で分かることも多い。
関連記事
>【絶対に離婚したくない(31)】相手からの離婚調停(6)ー改善策の組み立て方
>
>【絶対に離婚したくない(33)】相手からの離婚調停(8)ー相手弁護士がいきなり調停を起こしてきた思惑は?
>
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: