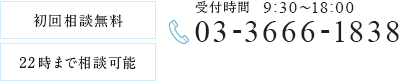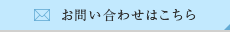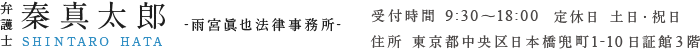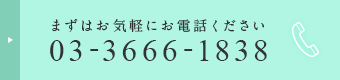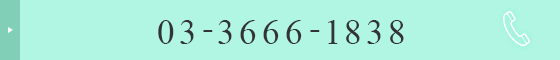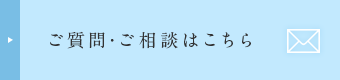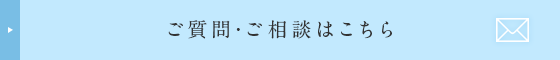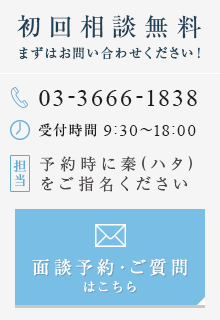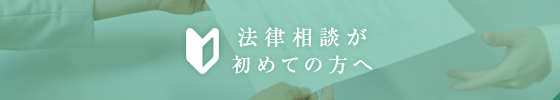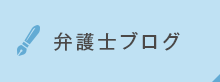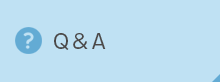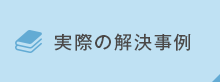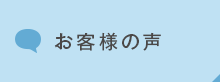【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(13)】夫婦円満調停を申し立てるかどうかの9個のポイント
2025.07.28更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】
私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。
それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。
①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている
②親の事情で片親というのは子供が不憫
③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう
④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変
⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)
⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい
⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任
⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず
⑨世間体、周囲の目が気になる
このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。
以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。
1.そもそも、夫婦関係円満調整調停って何だ?
夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
調停は、裁判所庁舎内の調停室(会議室のような部屋)で行われます。
なお、調停は夫婦同席ではなく、基本的にご夫婦が別々に調停室に入室する形で行われます(一方が話をしている間は、他方が待合室で待機している形を取ります)
2.夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイントって?
上記の通り、夫婦円満調停は、夫婦の話し合いを多数取り扱う調停委員が間に入ってくれますので、一面では大変便利な制度と言えます。弁護士を雇うよりも、調停を申し立てたほうが費用面からも非常に安価で済みます。
他方で、裁判所を利用した手続きになりますので、呼び出しを受けた相手を無用に刺激してしまうというリスクなどもあります。
そのため、今回は夫婦円満調停を申し立てるべきかの9個のポイントを整理し、解説していきます。
3.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント1】極力直接の話し合いに努めるべき
この点は、私が一番よくご相談者様にお話させていただく内容です。
上記の通り、夫婦円満調停は便利な制度としての側面を有しますが、本来夫婦円満を目指すのであれば、最低限夫婦で直接コミュニケーションが取れる状況にまで回復させることを目標とすべきです。
今後もご夫婦として仲睦まじい家庭を目指すのであれば、直接話し合いをして問題を解決できれば、それに越したことはないでしょう。
ただ、夫婦円満調停が頭に浮かんだということは、ご夫婦同士で直接の話し合いが難しい状況にあるということでしょう。例えば、夫側がこちらの話を一切無視するとか、勝手に出て行って連絡も取りにくくなったといったケースも考えられます。
このように直接の話し合いが難しいケースでも、すぐに話し合いを諦めるのではなく、ご両親や兄弟姉妹といったお身内の方や、仲人、友人、職場の上司、大学時代の先輩その他知人関係の方で間に入ってくれる方や、夫婦の話し合いに同席してくれそうな適任者を探してみてください。
そのような方を間に入れることで、夫婦の本音を聞けるというケースもあります。
このように話し合いの方法などを工夫しても話し合いがうまくいかないという場合には、いよいよ夫婦円満調停も視野に入ってきます。
ただ、そのような場合でもいきなり調停を申し立てるのではなく、事前に夫側に予告したうえで調停を申し立てるようにしてください。夫としても調停まではしたくないという場合には、直接の話し合いに応じるケースもあるからです。
4.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント2】いわゆる「脅し」として活用するのはNG
たまに私のところに相談に来られる方の中には、夫婦円満調停を、いわば「脅し」と言いますか「自分が優位に立つ道具として利用しよう」としている方もいます。
要するに、夫婦円満調停を起こすと、裁判所から夫に対して呼出状が届きますので、そのことで夫側をびっくりさせて優位に立とうとするのです。
確かに、夫の言動や行動、やり方が気に入らないというときに、夫を牽制するために夫婦円満調停を起こしたいという気持ちは分からなくはないのですが、夫を驚かせようという姿勢は、かえって夫婦関係修復を遠のかせてしまうと思います。
また、夫婦円満調停は他の「ポイント」で指摘しております通り、様々な検討要素がありますので、少なくとも安易に「脅し」のような目的で申し立てることは控えるべきだと思います。
5.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い
調停委員はあくまで中立な立場からご夫婦のお互いの話を聞いてくれます。
しかしながら、現在家庭裁判所で取り扱う調停事件の大半は離婚調停事件でして、夫婦関係の離婚で調停が解決するケースが圧倒的多数です。
このように離婚で事件を処理している関係で、調停委員は、残念ながら夫婦円満での話し合いには熱心ではないことが多いです。
調停委員が良く口にしますのが「夫婦円満での方向で相手も意見が一致していれば良いのですが、意見が一致しませんと、これ以上話を進めることが出来ないんです」といったフレーズです。
そのため、相手の夫側があくまで離婚を声高に主張しますと、例えば、2回目の調停期日にて、調停を取り下げるか、離婚の方向で考えてみてくださいといったことを真剣に考えなければならなくなるケースすらあります。
6.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント4】離婚調停に衣替えされるリスク
前述のように、夫があくまで離婚を声高に主張しますと、実際の調停の場での話し合いが、離婚に向けての話し合いに変容してしまうリスクがあります。
特に、調停委員から調停取り下げか、離婚に向けての話し合いを要求されてしまいますと、円満のために調停を申し立てたのに、離婚条件の話し合いに来ているようだと感じてしまうことも多々あります。
このような方向での話し合いになってしまいますと、夫側からの離婚ペースに載せられる危険性があり、残念ながら、離婚に向けての手続きが促進してしまうリスクがあります。
7.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント5】こちらの本気度を示すことが出来る
特に夫が、自分がこうだと思ったらこうなんだと決めつけて行動するようなキャラクターの場合、こちらがいくらやり直したいと伝えても聞く耳を持たないケースも往々にしてあります。
そのような場合には、本気で夫婦関係を良くしていきたいという本気度を示すために調停という手段を取ることはあり得ます。
ただ、夫側からしますと、急に裁判所から呼び出しを受ける形になりますと驚くことが多いと思いますので、調停がどのような手続きなのかといった点は事前に伝えておいた方が良いと思います。
8.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント6】外面が良い相手への対策
特に、夫が外面を気にかけるようなキャラクターの場合、調停の席では紳士的にふるまおうとする結果、離婚というフレーズを調停の場では封印するという人もいます。
そのようなことを狙ったうえで、調停を申し立てるという方法もあり得なくはありません。
ただ、そのような場合には、夫側はそもそも調停に参加しないという対応をするケースも少なからずありますので、この点には予め留意する必要があります。
また、夫が自身の「体面」(面子)を非常に気にするようなキャラクターの場合、逆に、あなたの話している内容をほとんど否定してくる可能性もあります。なぜなら、あなたは夫婦円満のために、その前提として夫の問題点や言動・行動の問題を指摘しなくてはいけませんが、夫側からすると「体面」(面子)を害されたと感じる可能性があるからです。
そうなってしまいますと、調停の場が夫婦が言い争う場になってしまい、夫婦関係の修復ではなく、決裂の話し合いになってしまうリスクがあるのです。
9.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント7】調停という手続き独自の制約
調停には、手続きとしていくつか制約もありますので、この点は予め考慮に入れておく必要があります。
①期日が早くとも1か月おきに設定されること
調停期日は一般的に1か月おきくらいの頻度で開催されます。そのため、どうしてもテンポよく話し合いをするということが出来ません。
お互い冷却期間を置くという意味で、焦らずに進めたいという場合には良いのですが、やや手続きが間延びしてしまう感は否定できません。
②夫に「調停の場で話そう」と誤魔化されるリスク
こちらから調停を起こしている手前、直接話をしようとすると、夫から「そっちが調停を起こしているのだから、調停の場で話をしよう」と返答されてしまいますと、なかなか調停の外での話し合いの場をセッティングしにくくなる面があります。
③平日の日中しか調停期日をセッティングできない
調停期日は、平日の日中にしか開催できません。そのため、調停を起こすと仕事をしている方は、仕事を休むか早退するなどして対応する必要がありますが、例えば、夫が普段から仕事が忙しいというような場合には、「どうしてわざわざ平日休みを取ってまで調停に行かなければならないんだ!?」と思ってしまうリスクがあります。
④毎度裁判所に足を運ばないといけない
調停は基本的に家庭裁判所内の調停室で行われますので、期日のたびに毎回裁判所に足を運ぶ必要があります(あなたが住む住所地が家庭裁判所からかなり遠いような場合には例外的にWEB会議方式にすることもできるのですが、そのような事情がない限りは、基本的には対面式で調停は行われます)。
特に調停室内の雰囲気が無機質というわけではないのですが、普段行かない裁判所に足を運ぶことが精神的負担ではないかというと、ある程度負担に感じる方の方が多いと思います。
10.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれば調停委員は非常に心強い
前述のように、夫側が、あくまで離婚にこだわるという場合には、夫婦円満での調整は難航してしまいますが、他方で、相手も円満方向での話し合いを了解した場合、調停委員は心強い味方になってくれることが多いです。
夫婦がお互いに円満な家庭を目指すというのであれば、調停委員も夫婦円満に向けてしっかりと協力してくれるからです。
その場合には、調停委員が専門知識を用いて、夫婦としてどのような点を改善していけばよいのか、どのように生活を営んでいくのが良いのかといった点をいろいろとアドバイスしてくれますので、非常に心強いです。
11.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント9】相手が離婚調停を起こしてきているときの有益性
よく、相手から離婚調停を申し立てられた際に、「これに対抗して、こちらから円満調停を申し立てたいと思うのですがどうでしょうか?」というご相談を受けることがあるのですが、結論から言いますと、ほとんど意味はありません。
なぜなら、離婚調停の手続きの中で円満に向けての話を持ち掛けることはできますので、円満調停を起こす意味合いがないからです。
このような技術的なところに目を向けるのではなく、夫婦関係を修復させるためにあなたはどのようなことをして行けるのかといった改善点の集約に全力を注いだほうが良いと思います。
12.まとめ
・【ポイント1】まずは、極力直接の話し合いに努めるべき
・【ポイント2】いわゆる「脅し」として利用することはNG
・【ポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い
・【ポイント4】離婚調停に衣替えされるリスクがある
・【ポイント5】調停を申し立てることで、こちらの円満に向けての本気度を示すことが出来る
・【ポイント6】相手が、外面が良いと紳士的に対応してくる可能性もある
・【ポイント7】調停手続きである以上、調停の席でしか話ができないとか、期日が間延びするといった制約がある。
・【ポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれが調停委員は非常に心強い
・【ポイント9】相手から離婚調停を起こされている場合、敢えてこちらから円満調停を起こす有益性は低い
関連記事
>【初めてでも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース
>
>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば、平日夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: